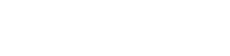田沼幸子
まだ私が院生だったときに、やはり別の大学で人類学を学ぶ同世代の女性がつぶやいた言葉だ。いったん社会人を経てから進学し、勉強しながら働いていた。
院のゼミというのは、たいていの場合、それなりに読み応えのある文献を読む。
英語であればなおさらだ。書かれた単語を辞書や事典で調べても、筋が分からないし、初年度など議論の内容が全然分からない。「先輩たちの話が宇宙人の話みたいだった」と思い起こす人もいた。先生の解説も正直、よく分からない。ただ、背景について人間的な裏話があると、なんとなく親しみが沸く。終わったあと、院生室のドアが閉まり、先生がいなくなったところで一息ついて、「いまの分かった?」と顔を見合わせるのが常だった。
それでも、大学の同級生が社会に出て、一人前に稼いでいることを時にうらやましく思っても、人類学を学ぶことは何かそれには代え難い特別なことに思えた。週に一度の(※東京都立大学はもっと多いです)院ゼミはドキドキする時間だった。そもそも、なぜその論文や本を読むのかすら分からない。時には、というより、しばしば、人類学者ではない人が書いたものも読む。それでも、この論文やこの本の先には、きっと、何かあるのだと読み、聞き、話し続けた。
それから2、3年で、院生はついにフィールドワークに出かける。人類学者にとってのフィールドワークは、数日とか数ヶ月という単位でも、できたらいいね、というオプションでもない。年単位でフィールドとするところに住み込むことがデフォルトである。外国であれば新しい言語を学び、使えるようにならないといけない。生まれ育った環境と大きく異なる人たちの間に住むのならば、新しい習慣や作法を学ばなければならない。子供のように間違え、笑われながら、周囲の人とぶつかったり、許し、許されたりしながら、あらゆることをノートやパソコンに書きとめていく。
そうして2年ものフィールドワークをしても、大学から去っていく人もいる。せっかくの助成金や奨学金がもったいない・・・と思ったが、当の本人たちはふっきれた様子だ。冒頭の彼女からも、数年後、外国での新しい仕事を報告する年賀状が送られてきた。他にもやはり、フィールドワーク後、別の仕事に就いた先輩がいる。久しぶりに再会すると、懐かし気に言った。「院生室で話してたことって、すっげー高尚だったよ、今思えば」。
カリブ海諸島、とくにプエルトリコで調査を行ったシドニー・ミンツは、フィールドワークは孤独なもの、死に似たものだという。しかも、死は一度きりで済むが、フィールドワークはそうではない、と。1960年代、人類学が「科学」と自己を位置づけ、対象からのデタッチメントを重視するなか、彼はインフォーマントのひとりを「友人」と書き、それさえなければいい本だったのに、と批判されたライフヒストリーを著した。そのような背景からすれば、フィールドワークが孤独だという言葉は、意外なものに思える。
でも、確かにフィールドワークは孤独だ。いつも人に囲まれ、巻き込まれているけれど、自分はその一部ではない。参与しながらも観察し、ノートに書きとめ、いつかそれをホームの人たちに分かるように書かなければならない。でも、結局、何も捉えられていないのではないかという焦りと不安に、つきまとわれながら。
帰国すると、そこにはまた、ゼミを前にして文献を読み、ため息をつく院生たちがいる。そして、久々に帰ってきた私たちを見て、おお、どうでした?と聞く教員がいる。少しずつ、語り始めると、フィールドでは得られなかった頷きと感嘆と疑問の声が返ってくる。
そのとき初めて、人類学徒は、自分が一人ではないと、感じられるのかもしれない。
あるいはこうとも言える。ゼミで息が吸える、と感じた彼女(たち)は、書物と研究室で十分に一人ではないと感じることができた。でも、フィールドまで行き、帰国してもなお、学問的な形にそれをまとめようとしている私たちは、まだ見ぬ仲間を求めて、それを行っている。調査後、研究会を立ち上げ、映画をつくり、民族誌を書いたあとになって、私はそのように感じる。人類学に惹かれる人は、きっと、何となく生きにくさや孤独を感じているけど、それが何なのかはっきりは分からない人たちだ。それが、徐々に、先人の調査や発見を通じて、さらに自らのフィールドワークとその表現によって、昇華されていく。
だれもがハッピーな社会なんて、存在しない。様々な人びとが自らをとりまく非合理や困難と折り合いをつけて生きていく様から、私たちはなにがしかを学ぶことができる。何が、私を息苦しくさせているのか。もし疑問に感じたら、人類学の扉を開いてみてほしい。処方箋ではない。でも、別の何かに出会えるかもしれない。保証はできないが。