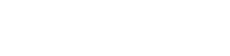2023年4月11日更新
東京都立大学人文社会学部では、学部2年次から専門コース・分野に進みます。社会人類学教室(社会人類学分野)は、各年度、最大19名の新2年生を受け入れています(定員をこえる希望者がいる場合には、1年次の成績を基準に選抜しています)。
社会人類学分野への所属を希望する1年生には、「文化人類学A・B」「フィールドワークからみる現代世界」の履修を推奨しています。
新2年生は、「社会人類学基礎演習」(少人数ゼミ)と「社会人類学A・B」(講義)を履修し、社会人類学の基礎を学びます。「社会人類学基礎演習」は、少人数教育実現のため、2クラス制を採用しています。「社会人類学基礎演習」では、夏休みの研究成果を発表する場として、9月下旬から10月初旬に恒例の合同ゼミ合宿を実施しています。
「演習」科目(文化人類学演習I、II、社会人類学演習I、民俗学演習、地域研究演習、民族誌研究演習)は、各教員がそれぞれのテーマで開講するゼミ科目です。社会人類学分野では、複数のゼミを履修することを推奨しています。「社会人類学演習II」は、調査実習科目です。これまで、伊豆諸島、佐渡島などでの調査実習や、映像制作実習を実施しています。
4年生は、卒業論文にとりくみます。
社会人類学分野提供科目一覧
2023年度の社会人類学分野提供の授業科目は、次のとおりです。
必要度Aの科目は必修科目、必要度Bの科目は必修選択科目に相当します。
| 授業科目名 | 単位 | 必要度 | 履修 年次 |
担当者 | 授業内容 |
|---|---|---|---|---|---|
|
基礎ゼミナール
|
2
|
A
|
1
|
田沼 |
|
|
文化人類学A
|
2
|
A
|
1, 2
|
綾部 |
全学基盤科目(社会人類学分野推奨科目)
|
|
文化人類学B
|
2
|
A
|
1, 2
|
河野 |
全学基盤科目(社会人類学分野推奨科目)
|
| フィールドワークからみる現代世界 |
2
|
B
|
1, 2
|
全教員 |
全学教養科目(社会人類学分野推奨科目)
|
|
(基)社会人類学基礎演習
|
4
|
A
|
2, 3
|
石田 |
社会人類学基礎文献の講読
|
|
(基)社会人類学基礎演習
|
4
|
A
|
2, 3
|
深山 |
社会人類学基礎文献の講読
|
|
(基)社会人類学A
|
2
|
A
|
2
|
河合 |
異文化理解の理論・方法・学説史
|
|
(基)社会人類学B
|
2
|
A
|
2
|
綾部 |
異文化理解の理論・方法・学説史
|
|
※民俗学特殊講義
|
2
|
B
|
2, 3, 4
|
塚原* |
民俗文化
|
|
※地域研究特殊講義
|
2
|
B
|
2, 3, 4
|
田沼
|
マルチモーダル民族誌の歴史と現在 |
| ※民族誌特殊講義 | 2 | B | 2, 3, 4 | 深山・河野 | オセアニア社会文化論 |
|
※文化人類学特殊講義
|
2
|
B
|
2, 3, 4
|
デサンモーリス* |
文化研究の視点と方法
|
| ※社会人類学特殊講義 | 2 | B | 2, 3, 4 | 石田 | 社会人類学の応用 |
| ※社会人類学特殊講義 | 2 | B | 2, 3, 4 | 河合 | 社会人類学の方法 |
|
※文化人類学演習I
|
4
|
B
|
2, 3, 4
|
深山
|
社会研究の最前線とスキル(深山ゼミ)
|
|
※文化人類学演習II
|
4
|
B
|
2, 3, 4 |
綾部
|
世界システムと文化の現在(綾部ゼミ)
|
|
※社会人類学演習I
|
4
|
B
|
2, 3, 4 | 石田 |
社会組織・社会構造(石田ゼミ)
|
|
※社会人類学演習II
|
4
|
B
|
2, 3, 4 | 全教員 |
フィールドワーク演習
|
|
※フィールド文化論演習
|
4
|
B
|
2, 3, 4 | 河合 |
東アジア社会文化論(河合ゼミ)
|
|
※地域研究演習
|
4
|
B
|
2, 3, 4 |
田沼
|
地域研究の現代的課題(田沼ゼミ)
|
|
※民族誌研究演習
|
4
|
B
|
2, 3, 4 |
河野
|
民族誌研究の現代的課題(河野ゼミ)
|
|
民俗学実習
|
2
|
B
|
3, 4
|
浅野*
|
民俗学の理論・方法・学説史
|
| 社会調査の国際比較 |
2
|
B | 3, 4 | トサクン* | 社会調査方法の比較検討 |
|
社会人類学特論演習
|
4
|
A
|
4
|
全教員
|
卒業論文作成の指導
|
|
卒業論文
|
10
|
A
|
4
|
全教員
|
卒業論文作成
|
(基):主に2年次対象の基礎的な専門教育科目。
※ :内容の異なる場合には重ねて履修できる科目。
氏名* :非常勤講師。
2022年度シラバスはこちら
授業紹介(2023年度シラバスから)
綾部ゼミ(文化人類学演習II)
アメリカにおける特に重要な社会問題を掲載したAmerican Issues: Every American Has an Opinion(2013)および、文化人類学の初学者のために編まれた英語のサブリーダーであるAnnual Editions: Anthropology(42nd edition, 2018)のなかのアメリカに関する論考を主として用い、アメリカという国家と同国を構成する人々の多様な価値を人類学的な観点から包括的に理解することを主眼とする。また、アメリカを様々な角度から表象した映画、テレビドラマ、サブスクリプション系ドラマなどを併せて視聴することで、フィクションを現実理解の一助とするための観点も学ぶ。
石田ゼミ(社会人類学演習I)
本演習は、主に学部3、4年次生を対象に、社会人類学における古典的著作の講読と参加型ディスカッションを行なう。本年度は、ヴィクター・ターナー『儀礼の過程』の輪読からはじめる。
河合ゼミ(民俗学演習)
社会人類学および民俗学の視点から、東アジア社会文化の多様性を理解する。前期では、中国本土および台湾の民族的状況を概観したうえで、東アジアの民族文化について理解を深める。後期は台湾または日本を主要な対象とし、フィールドワークに基づき多民族的・多文化的世界を理解する。
河野ゼミ(民族誌研究演習)
本演習のテーマは「モノと身体」である。人間の暮らしはモノと不可分であり、人はモノを利用しながら暮らしを営むと同時に、モノに囲まれながら日々を過ごす。また、人間は身体的な存在であり、自らの身体とともに生きていかなければならない。私たちがモノや身体とつきあう場面は、日々のコミュニケーションから、ファッションと装い、スポーツや音楽などのパフォーマンス、宗教・儀礼的な実践、病気と向き合う状況に至るまで、非常に多岐にわたる。人類学はこうした人とモノと身体の関係性をどのように扱うことができるのか、関連文献の輪読や身近な対象への接近を通して考えたい。モノと身体という地平から拓ける展望の広さを理解することも、本演習の1つの狙いである。
田沼ゼミ(地域研究演習)
外国(キューバ・スペイン)について学ぶ。その知識と見方を通じて、「大人になる」「社会に出る」とはどういうことかを、日本という国だけでなくグローバルな視野から考える。
深山ゼミ(文化人類学演習I)
『日本の先住民アイヌについて学ぶ・考える』最近は、2019年のアイヌ施策推進法の制定、2020年のウポポイ開園が続き、さらに漫画・アニメや小説や映像などにおいて取り上げられる機会が増えたこともあって、アイヌについて見聞きする機会が増えた。しかし、私たちはアイヌという人びとについて、なにを知っているだろうか。あるいは、アイヌについて知ることによって、社会科学におけるどのような問いに辿り着くことができるのだろうか。長引くコロナ禍によって内向き志向が強まっていることが指摘される今、あえて日本を「内側」そして「周辺」から問い直すことを目的に、先住民アイヌに関して学び考える。
全教員担当ゼミ(社会人類学演習II)
社会人類学はフィールドワークを主要な方法論とする学問である。したがって、主体的な学習のためには、フィールドワークに特有の技法や姿勢を身につけることが不可欠である。本演習では、フィールドワークの過程を実践的に学ぶため、日本国内における短期の調査合宿を授業の中心に位置づける。具体的には、受講生が各自/各班の関心に沿って調査計画を立案したうえで、教員の引率のもとで調査合宿を行い、その成果を最終的なレポートとしてまとめる。この実践を通して、事前の準備から現場での情報収集、事後の作品づくりに至るまでの一連の過程を試行錯誤しながら経験し、フィールドワークに不可欠なスキルを身につけることを、本授業の目的とする。
卒業論文
卒業論文執筆要綱(2015年度版)
はじめに
本要綱は、卒業論文の執筆に際してのガイドラインとして作成されたものである。したがって、書式不備を理由に卒業論文を不可にするための絶対的なルールではない。細部については、随時指導教授と相談しながら進めていってほしい。卒業論文の成否は、在籍した4年間の最終的な充実度を左右する重要なものである。諸君がなんらかの達成感とともに執筆を終え、晴れ晴れとした気持ちで卒業していくことを願う。
A 基本的様式
1. 分量
20,000字以上(400字詰原稿用紙50枚相当以上)とする。手書きは不可。
*本文末尾に総文字数を明記する。
*英文での執筆を希望する場合のワード数等については指導教授に相談すること
2. 1ページあたりの字数・行数
40字×36行(1,440字相当、ワードの初期設定に同じ)とする。
*製本時の見やすさを考慮して、左側の余白を十分に設けること。
3. 用紙等
A4版の用紙を縦で使用。片面印刷。横書き、左綴じとする。
4. 使用ソフト
原則としてMS-WORD(Windows版、 Mac版)を用いる。
*それ以外のソフトを用いるときには指導教授と相談すること。
5. フォント
原則として日本語についてはMS明朝(10.5ポイント以上)、英数字についてはCentury(10.5ポイント以上)を用いることとするが、必要に応じてゴシック体や別のフォントを使うことを妨げない。
6. 書式
引用文献の提示の仕方、参考文献リストの作成といった書式については、日本文化人類学会が発行する学会誌『文化人類学』(旧民族学研究)の「執筆細則」に準ずること。
※ただし、要旨・二段組は不要
B 装丁等
人文・社会系教務係の規定(2015年11月頃に掲示予定)にしたがう。
例年の形式は以下のとおり。
(1)フラットファイルA4版(黄色)
(2)縦書き、横書きいずれも可。鉛筆書きは不可。
(3)表紙および扉には論文題目、総ページ数(本文のみ実枚数:参考資料等がある場合は各自判断すること)、指導教授名、コース、分野名、学修番号、氏名を、本文にはページを記入すること。
(4)論文題名が外国語の場合は、表紙および扉に日本語訳を併記すること。
C 構成
論文は、原則として以下の構成をとるものとする
(※印は必須要素。必須要素がひとつでも欠けている場合には書式不備とみなす)。
・表紙(※) 上記の書式に従うこと
・目次(※) 章、節、項などに分け、各々の開始ページを明記する
・図表一覧・略語集・用語集・凡例等
・本文(※) 最低2章以上で構成すること
・謝辞
・注(※) 事項注のみ、脚注として各頁下部に来る場合もあり
文献注の付け方については、「執筆細則」を参照
・参考文献(※) 詳細については「執筆細則」を参照
・参考資料一覧、Web Site一覧 新聞記事、一般誌の記事、Web Siteなどの情報を使用した場合。なお、Web Siteを参考資料として提示する際は、①サイト名、②管理者名(ない場合は省略可)、③URL、④サイトの最終更新日もしくは執筆者による最終閲覧日を正確に記入すること。
・附録(参考資料、図表など)
リソース