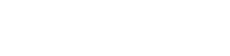2023年12月15日、東京都立大学社会人類学会編『社会人類学年報』49号を刊行しました。
社会人類学年報49号目次
『社会人類学年報』記念号の刊行にあたって
佐々木重洋 「ブッシュの霊魂」の物質性と融即の美学
[特集]中東民族誌の現在:イスラーム、近代、ジェンダー
大川真由子 序:中東・イスラーム人類学の課題
赤堀 雅幸 中東民族誌の四半世紀を振り返る
池田 昭光 さよなら、イスラームの人類学:サムリ・シールケの所論をめぐって
嶺崎 寛子 ジェンダー・オリエンタリズムと中東人類学:民族誌の消費と需要をめぐって
荒木 亮 「混成」という視点:宗教復興のダイナミズムを描き出すということ
齋藤 剛 中東に生きる人々に学ぶ:現場主義の精神と「非境界型世界」
岩瀬 裕子 [調査報告]「基盤的コミュニズム」のゆらぎと調整:スペイン・カタルーニャ州バイスにある「人間の塔」の継承集団を事例に
松岡 竜大 [新刊紹介]宮岡真央子・渋谷努・中村八重・兼城糸絵(編)『日本で学ぶ文化人類学』
[研究短報]
板久梓織、田井みのり、小宮理奈、渡邊泰輔
2023年12月22日:博士論文口頭試問を開催
2023年12月22日に社会人類学分野博士論文口頭試問開催します。
日時:2023年12月22日(金)14:00~16:00
会場:5号館1階143(小会議室)
寺尾 萌(鹿児島大学・特任研究員)
モンゴル西部牧畜地域における「出会い」の技法に関する人類学的研究
主査:綾部 真雄(東京都立大学・教授)
副査:田沼 幸子(東京都立大学・准教授)
河野 正治(東京都立大学・准教授)
東京都立大学大学院人文科学研究科社会行動学専攻
社会人類学教室
2023年10月20日:テ・アロハ・ラウントゥリー先生講演会を開催しました
去る10月20日(金)の3限に、深山直子担当の学部ゼミ「文化人類学演習Ⅰ」において、アオテアロア・ニュージーランドより先住民マオリ研究者であるテ・アロハ・ラウントゥリー先生をゲスト・スピーカーとしてお迎えしました。現在フランスでラグビーのワールドカップが開催されていることから、オールブラックスが試合前に行うことで有名なハカについて話題提供を頂きました。ハカはその人気から、今や国内・世界各地にて多様な場面で行われるようになっています。それは果たして、マオリ固有の文化の盗用なのでしょうか、あるいは称賛のかたちなのでしょうか?ラウントゥリー先生の問いかけは、参加した学生を大いに刺激したようで、使用言語が英語だったにもかかわらず活発な質疑応答がなされました。
ゲスト・スピーカー:Te Aroha Rountree先生
Tribal affiliations – Ngai Tuteauru, Nga Puhi, Hokianga, Aotearoa
Senior Lecturer in Māori/Moana Studies, Trinity Methodist Theological College / Te Haahi Weteriana o Aotearoa
https://trinitycollege.ac.nz/why-trinity/who-we-are/
話題タイトル:”Haka Boogie!: Appropriation or Appreciation?”(「ハカをおどれ!:盗用か、あるいは称賛か?」)

2023年11月3日、渡邊欣雄名誉教授と高桑史子名誉教授が沖縄・読谷村にて講演
2023年11月3日、渡邊欣雄名誉教授と高桑史子名誉教授が下記の特別講座で講演します。
文化の日・世界のウチナーンチュの日 特別講座「文化人類学からみる沖縄移民」
日時:2023年11月3日(金)13:00~17:00
会場:世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム 1F講座室
渡邊欣雄・東京都立大学名誉教授「グローバル沖縄-ホスト&ゲスト-」
高桑史子・東京都立大学名誉教授「八重山に向かう人々ー移民がつくる八重山文化」
申し込み先(要事前予約)はポスターをご覧ください。
ポスターはこちら
2023年7月25日、河合洋尚准教授が2023年度大同生命地域研究奨励賞を受賞しました
2023年7月25日、河合洋尚准教授が、公益財団法人大同生命国際文化基金「2023年度 大同生命地域研究奨励賞」を受賞しました。
客家研究を単なる中国研究、華僑研究の枠組から拡張し、東アジアのみならず、東南アジア、オセアニア、ラテンアメリカ地域の客家コミュニティを対象にし、そこに客家空間を創造することでグローバル化に伴う世界の急激な構造変化に対応していく複雑な仕組みを明らかにしました。このようなグローバルな視野を地域研究に具体的に取り入れ見事に実践する手法は、21世紀の地域研究の新たな、そして豊かな可能性を体現していると評価されました(大同生命国際文化基金ウェブサイト記事より抜粋)。
東京都立大学ウェブサイト記事はこちら
大同生命国際文化基金ウェブサイト記事はこちら
2023年8月19日、綾部真雄教授が2023 年度日本地理教育学会出版文化賞を受賞しました
2023年6月15日:深山直子准教授のインタビュー記事が朝日新聞に掲載されました
2023年6月15日、朝日新聞・朝刊およびデジタル版の「(耕論)アイヌ民族と私たち」に、ニュージーランドの先住民マオリをめぐる状況と、日本の先住民アイヌをめぐる状況の違いについて、深山直子准教授のインタビュー内容が掲載されました。
2023年5月26日:社会人類学教室国際交流イベントを開催しました
2023年5月26日に下記の内容で社会人類学教室国際交流イベントを開催しました。
東京都立大学社会人類学教室とMetropolitan State University of Denver社会学人類学教室とは、2011年以来、教室間交流をしてきました。2、3年に1回、Metro State側から引率教員2名(Su Il Kim先生、Rebecca Forgash先生)と学生が来学し、社会人類学教室の教員・学生と交流しています。
今回は都立大開催の交流イベントとしては2012年、2014年、2016年、2019年、2022年(オンライン開催)に続く6回目のイベントで、2019年以来の対面開催です。前半はそれぞれの学生・院生による5本の発表、後半は、グループディスカッションをしました。
TMU-MSU Denver Anthropology Workshop (東京都立大学社会人類学教室国際交流イベント)
場所:国際交流会館 大会議室
9:30-10:00 Reception
10:00-10:05 Welcoming Remarks by Dr. Sachiko Tanuma
10:05-10:10 Opening Remarks by Dr. Rebecca Forgash
10:10-10:15 Self-introduction of faculty members
10:15-10:30 Nova Kor ‘My experience working at the Museo de las Americas’ (10-minute presentation + 5-minute Q&A)
10:30-11:00 Asuka Tamura ‘Plurality of Self as ‘Dark History’: Adaptation to Hierarchy in Schools’ (25-min presentation + 5-minute Q&A)
5 min. break
11:05-11:35 Katrina Geist ‘Cultivating connection in the Covid era: student experiences in an in-person agroecology internship after experiencing pandemic learning’ (25-min presentation + 5-minute Q&A)
11:35-12:05 Shoko Mori ‘The incompleteness of collaboration and ethnographic practice:
A case study of the exhibition “‘How do you see the world?’: the Art of Almighty God”‘ (25-min presentation + 5-minute Q&A)
12:05-12:15 Raine Barker, Marissa Erickson, Sophie Gordon ‘COVID-19 and Social Connection: A Visual Ethnography’ (Seeking Participants) (8-10 minute explanation of research and request for participants)
12:20-13:30 LUNCH13:30—14:30
Show & Tell (Divide into groups of 4-5 people, show and tell about what they brought. Change the group member once or twice).
14:30-14:37 Overall Comments by Dr. Su Il Kim
14:37-14:45 Closing Remarks by Dr. Masao Ayabe
2023年7月8日:人文科学研究科社会人類学教室オンライン説明会を開催
東京都立大学大学院人文科学研究科の社会人類学教室では、2023年7月にオンライン説明会を実施します。事前申込制です、下記をご参照下さい。
【社会人類学教室】
実施時期:2023年7月8日(土)10時~11時30分(予定)
申込期間:7月2日(日)まで
申込方法:こちらからログインし、必要事項を入力のこと。
Zoomへの参加方法:事前に申込者へメールで連絡
その他:希望に応じて、当日にZoomによる個別相談も実施
2023年4月21日:海域アジア・オセアニア研究プロジェクト東京都立大学拠点のウェブサイトを公開しました
海域アジア・オセアニア研究プロジェクト東京都立大学拠点のウェブサイトが公開されました。現代海域アジア・オセアニア世界における人と物質の流動を中心テーマとして、今後も活発な研究活動を展開していく予定です。https://www.maps.jinsha.tmu.ac.jp/